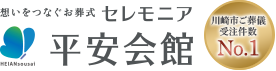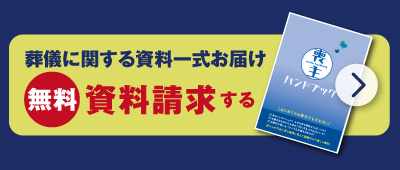初盆と一周忌、優先度が高い法事はどちら?
初盆と一周忌を一緒に行うのはタブーかどうかも併せてご紹介
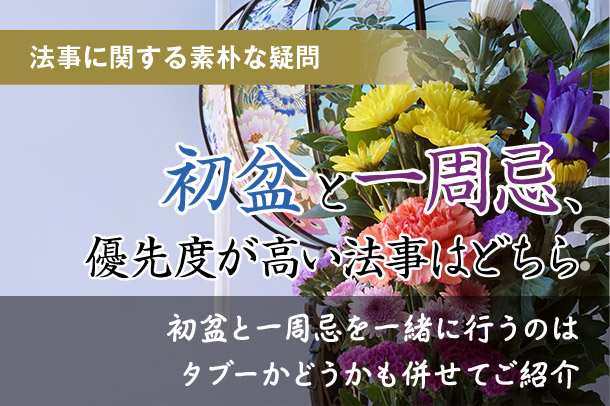

そろそろ初盆の季節も近くなり、この一年程で喪に服されたご遺族の中には初盆の準備を始められている方も多いことかと思います。
前年のお盆前後で故人様を見送られた方の中には、初盆と一周忌が同じ時期となるためできれば一緒に行えれば、とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、初盆と一周忌を同時に行うことが一般的なのか、それともタブーとされているのか、あまり知られていないのが現状です。
ここでは、初盆と一周忌の優先度や、初盆と一周忌を同時に行うことが可能かどうか、お盆の時期のトピックとしてご紹介します。
1.初盆と一周忌について
1-1. 初盆とは
故人様が亡くなってから初めて迎えるお盆のことです。故人様の霊が初めて里帰りするお盆であり、通常のお盆よりも丁寧に供養を行います。
一般的に8月13日〜16日に執り行われるものですが、東京等一部地域では7月中に行うこともあります。
ご遺族や親族、時には故人様の友人・知人等も招いて、僧侶にお経をあげてもらうといった仏教的な儀礼を行うのが一般的です。
1-2. 一周忌とは
故人様が亡くなってからちょうど1年後に営まれる仏教の法要です。
忌日法要のひとつで故人を偲び冥福を祈るため、ご遺族や親族、故人様に近しい方々をお招きし、僧侶に読経を依頼しその後参列者に食事の場を設ける等の特別な供養を行います。
1-3. 優先度が高いのはどちらか
地域によって考え方の違いはありますが、概ね一周忌の方が初盆より優先度が高いものとされています。
仏教の場合は特に忌日(命日)を重んじる考え方があり、一周忌はその命日を基準にして行われるため、法要を行う際は一周忌を優先して考えるべきだと言われてます。
2.初盆と一周忌を一緒に行うことについて
それでは、初盆と一周忌の時期が重なる場合、2つの法事を併せて行うことは可能なのでしょうか。
2-1. 一緒に行うことは可能
多忙を極める現代においては、多くの家庭や寺院でも日程や準備の都合を考えて、初盆と一周忌を合同で行う機会が増加傾向にあります。
この場合お盆(対象となる故人様は初盆)はすべての先祖の供養を目的とし、一周忌は故人様の満一年の供養になります。
2つの法要の時期が重なる場合、合同法要として執り行うことに問題はないとされています。
3.一緒に行うときの注意点
3-1. 日程調整・寺院への確認
1-3.でご紹介した通り、法要の優先度としては一周忌が高いので、まず一周忌を優先してスケジュールを調整し、それに併せて初盆を行うとすると良いでしょう。
一周忌をお盆の時期に合わせて前倒しで行うこともありますので、菩提寺や僧侶へ初盆と一周忌を同時に行う旨を事前に相談することが必要です。
また、お盆の時期が一周忌より大幅に後ろ倒しになる場合は一周忌と併せて行わずに個別で法要を行う方が良いと言われています。
しかし川崎市といった首都圏で行う法要ですと、昔からのしきたりよりも現代の利便性に合わせるといった柔軟性を持たせた法要のあり方を支持する方も増えていますので、迷われたらお世話になっている寺院等に相談してみると良いでしょう。
3-2. お布施はどのくらい宗教者にお渡しすべきか
宗教者へお渡しするお布施は併せて行なったとしても、初盆・一周忌の法要それぞれの分をお渡しするのが一般的です。
宗派によっても様々ですが、首都圏では概ねそれぞれ3万円〜5万円程度を包むのが通例とされているようです。
3-3. 参列する場合、香典の金額はどのくらいが良いか
逆に初盆と一周忌を同時に行う法要へ参加される場合、お渡しするお香典はどのくらい包めば良いのでしょうか。
3-2.で触れた宗教者への香典とは異なり、2つの法要分を併せて包んで良いでしょう。
その場合は、一般には初盆もしくは一周忌を単独で行う際にお渡しする金額より若干多めに包むのが良いと言われています。
ただし、このケースでも忌数(偶数や4や9といった縁起の悪いと考えられている数字)は避けるのがマナーです。
まとめ
初盆と一周忌を合同で行う法要は、近代のライフスタイルの変化により取り入れられた比較的新しい供養のスタイルだと言われています。
今後も時代と共に新しい供養の形が取り入れられていくと思われますが、根本にあるのは故人様に手を合わせ冥福を祈ること。
これから迎える未来にも、引き継いでいきたいものですね。
平安会館では葬儀にまつわる様々な事前相談をお受けしております。
ご不安やお困りのことがございましたら、どのようなことでもお気兼ねなくご相談ください。
また、いざという時に役立つ内容を盛り込んだ「喪主ハンドブック」を無料でお届けしておりますので、こちらもお気軽に資料請求よりお申し込みください。