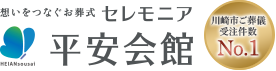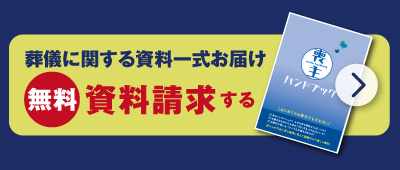葬儀を避けるべき日、その理由について
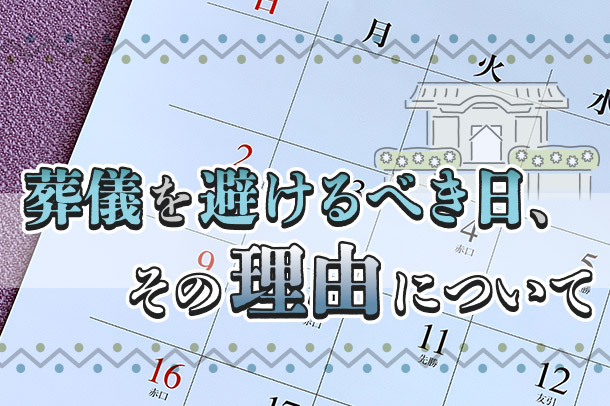

葬儀の日取りを決めるとき、多くのご遺族が「縁起の良い(悪い)日の葬儀は避けるべきだろうか」「避けるべき日があるのかしら」と迷われるかと思います。
実際、葬儀を執り行うにあたり、宗教的な決まりや地域の慣習、さらに火葬場や葬儀場の運営状況など、さまざまな要素が関わってきます。
ここでは葬儀を避けるべき日について、宗教・事由別にご紹介します。
1.仏教における葬儀を避けるべき日
仏教式の葬儀には、本来「避けるべき日」という宗教的な決まりはありません。
ただし、寺院で行われる仏教の年中行事(彼岸、お盆、涅槃会、成道会など)の法要日や、お寺の大切な法要と重なる日程となる場合は、この日を避ける日程で葬儀が執り行われます。
2.神道における葬儀を避けるべき日
神道には「忌日(きにち)」という考え方があり、亡くなってから50日間を特に慎む期間とされています。
そのため、近親者が亡くなった日から 50日間を「忌中」とし、この間は神社への参拝や祭典への参加を控える習わしがあります。
ただしこの期間は葬儀自体を行えないというわけではありません。
忌中は葬儀を避けるというより、ご遺族自身が神事に参加できない・参拝を控える期間という意味合いが強いようです。
また、大祭(例祭日)など神社にとって重要な祭礼のある日は葬儀を避ける傾向があります。
3.キリスト教における葬儀を避けるべき日
キリスト教式の葬儀にも、本来「避けるべき日」という宗教的な決まりはありません。
ただし、日曜の礼拝時間やクリスマスや復活祭といったキリスト教の大祭日といった教義上特別な日時では、葬儀を行わないか日・時間をずらして行うことが一般的です。
4.なぜ友引の日は葬儀を避けるのか?
「友引」は六曜のひとつで、暦に記される日ごとの吉凶(縁起の良し悪し)を示す占いの一種です。宗教的な意味合いはありません。
六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)はもともとは中国で生まれた暦注で、日本には鎌倉時代〜室町時代に伝わったといわれています。
現代の日本では、冠婚葬祭や引っ越しの日取りなどを決めるときに参考にされることが多いようです。
友引の本来の意味は「共引き(引き分け)」で、勝負ごとに吉凶がつかない日を表していました。
しかし日本では文字の意味や言葉の響きより「友を引く」と解釈されるようになり、この日に葬儀をすると「故人が友を道連れにする」という迷信が広まりました。
そのため、多くの地域では友引の日に葬儀を避ける習慣が根付くこととなりました。
参考までに、六曜の種類と意味を簡単にご紹介します。
◆先勝(せんしょう/せんかち)
午前は吉、午後は凶。急ぐことが吉とされる。
◆友引(ともびき)
朝・夕は吉、昼は凶とされる。
◆先負(せんぷ/せんまけ)
午前は凶、午後は吉。急がず静かに過ごすのが良いとされる。
◆仏滅(ぶつめつ)
何をするにも凶とされる日。婚礼を避ける習慣がある。
◆大安(たいあん)
何をするにも吉とされる最良の日。結婚式などによく選ばれる。
◆赤口(しゃっこう/しゃっく)
午前11時〜午後1時のみ吉、それ以外は凶とされる。
現在では公営火葬場等でも「友引休業日」を設けるようになり、葬儀を避けるというよりは実務的に葬儀を行うことのできない日となっています。
まとめ
友引に葬儀を避けるのは、「友を冥土に引く」という言葉の連想から生まれた迷信がベースとなり現在に伝わったものです。
そのため科学的・宗教的な根拠はなく、日本独自の慣習として今日まで定着しているのです。
実際のところ、川崎市といった首都圏に住む方の中には「友引に葬儀を行うことについては特に気にしない・問題としない」という意見も近年増えてきているのも事実です。無宗教葬といった新しいお見送りの形を選ばれる方々は、特にその傾向が強いようです。
しかし、かわさき北部・南部斎場をはじめ公営火葬施設の多くが友引を休場日としている実務上の理由からも、結果的に友引を避けざるを得ないケースがほとんど。
葬儀の日取りを決める際は、宗教者や葬儀社に相談しながら、ご遺族の意向も尊重しながら柔軟に決めることが大切です。
平安会館では葬儀にまつわる様々な事前相談をお受けしております。
ご不安やお困りのことがございましたら、どのようなことでもお気兼ねなくご相談ください。
また、いざという時に役立つ内容を盛り込んだ「喪主ハンドブック」を無料でお届けしておりますので、こちらもお気軽に資料請求よりお申し込みください。